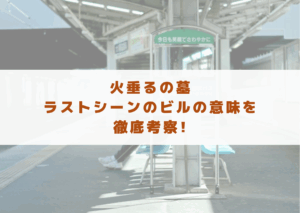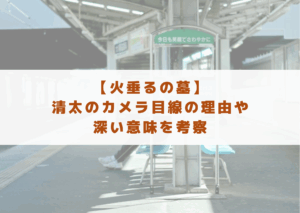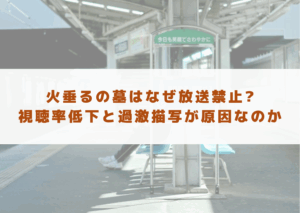映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(BTTF)は、1985年に公開されて以来、世界中のファンを魅了し続けるSF映画の金字塔です。タイムトラベルを題材にしたワクワクするストーリー、個性的なキャラクター、数々の名セリフと伏線が散りばめられたこの作品には、まだまだ知られていない小ネタや裏話がたくさんあります。
本記事では、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズにまつわる興味深い小ネタ20選をご紹介します!これを知れば、もう一度映画を見たくなること間違いなしです。さらに、それぞれの小ネタを掘り下げることで、映画に込められた制作陣のこだわりや、作品が持つ奥深さを考察します。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズは名作と呼ばれますが、劇中には、アメリカの深い闇や人種差別的な表現も含まれているのをご存じでしょうか?
アメリカ映画に関する深い考察に興味がある方は、『最も危険なアメリカ映画 『國民の創世』から『バック・トゥ・ザ・フューチャー』まで』がおすすめです。

少し難しい内容も含まれますが、アメリカ映画が好きな方は一読の価値ありです。知られざるアメリカの一面を知ることができますよ!
紙の書籍なら持ち運びには不向きですが、電子書籍なら気軽にスマホでサクサク読めちゃうのでお勧めです~♪
\ 初回ログインで70%オフ! /

映画鑑賞は年間100本以上・映画ブログ運営4年
中学生の頃に『スターウォーズ』に感動して以降、
映画の沼にハマり続けて20年。
結婚・出産後も年間100本は必ず鑑賞中。
Filmarksアカウントにも鑑賞レビューを掲載中。
1. デロリアンの代わりに冷蔵庫がタイムマシンになる予定だった?
最初の脚本では、タイムマシンは冷蔵庫として描かれていました。しかし、「子供たちが真似して冷蔵庫に閉じ込められる危険がある」との懸念から、車に変更されました。結果的にデロリアンのスタイリッシュなデザインが生まれたのです!
考察と感想
冷蔵庫がタイムマシンだった場合、映画の雰囲気は大きく異なっていたでしょう。移動の自由度が少なくなり、ストーリー展開に制約ができてしまったかもしれません。デロリアンの選択は、作品の視覚的インパクトを大きく向上させ、映画史に残る象徴的なアイテムになりました。
2. 1.21ジゴワットの誤解
ドクが叫ぶ「1.21ジゴワット(gigawatt)」ですが、実は発音ミス。「ギガワット」が正しい発音です。脚本の段階で間違えてしまいましたが、そのまま使われることになりました。
考察と感想
この間違いが逆に映画のアイコニックなシーンとして記憶されることになりました。言葉の誤用が、作品にユーモアを加え、ファンの間での話題作りに貢献していることは興味深いです。
3. マーティ役は別の俳優だった?
最初にマーティ役を演じたのはマイケル・J・フォックスではなく、エリック・ストルツでした。しかし、彼の演技がコメディ要素と合わず、5週間の撮影後に降板。マイケル・J・フォックスが急遽キャスティングされ、彼なしでは考えられない名作が誕生しました。
考察と感想
結果的にフォックスがマーティを演じることで、映画のテンポや雰囲気が大きく向上したといえます。もしストルツが続投していたら、作品の評価はまったく違ったものになっていたかもしれません。
4. ロナルド・レーガン大統領も映画の大ファン!
当時の米大統領であるロナルド・レーガンは本作の大ファン。特に、自身の名前が作中に登場するシーンを何度も見返していたとか。
考察と感想
映画が政治家にまで影響を与えるほどの人気作品だったことがわかります。レーガン大統領がスピーチで映画のセリフを引用したのも納得です。
5. 「チキン」という設定はPart2から!
マーティが「チキン(腰抜け)」と言われて怒るシーンはPart2から登場しました。実はPart1にはこの設定はなく、続編で追加されたものだったのです。
考察と感想
この変更により、マーティのキャラクターにより深みが増しました。彼の成長や弱点が明確になり、ストーリーの軸が強化されたといえます。
6. 未来予測が的中?
Part2では2015年の未来が描かれています。空飛ぶ車はまだ実現していませんが、フラットスクリーンテレビやビデオ通話など、驚くほど多くの未来技術が現実になっています。
考察と感想
SF映画が未来技術の予測を的中させることは珍しくありませんが、本作ほど正確に未来を描いた作品は少ないでしょう。科学技術の進歩に対する制作陣の洞察力の鋭さがうかがえます。
7. 隠れミッキー
Part1のオープニングで、ドクの時計コレクションをよく見ると、ミッキーマウスの時計があるんです。ディズニーファンにはたまらない発見ですね!
考察と感想
ディズニーとの関連を意識させる遊び心が、作品の親しみやすさを増しているといえます。こういった細かい小ネタが、繰り返し鑑賞する楽しみを与えています。
8. 3人のマイケル・J・フォックス
Part2の2015年シーンで、マーティは自分の息子と娘、そして年老いた自分を演じています。1人3役です!特殊効果を駆使して撮影されましたが、とても大変だったそうです。
考察と感想
俳優が同じシーンで複数のキャラクターを演じることで、未来のマクフライ一家のつながりが強調されました。これにより、シリーズ全体の統一感が生まれ、観客がマーティの未来を実感できるようになっています。
9. ヒューイ・ルイスのカメオ出演
映画の主題歌「The Power of Love」で有名なヒューイ・ルイス。実は、Part1でカメオ出演しているんです。オーディション審査員役で登場しますよ。見逃した人は、もう一度チェックしてみてください!
考察と感想
音楽と映画の融合が見事に表現されているポイントです。主題歌の歌手が登場することで、映画全体にリアルな空気感が生まれ、観客に深い印象を与えました。
10. ジョージ役の交代劇
Part2と3でジョージ役が変わっているのに気づきましたか?俳優のクリスピン・グローバーが降板し、別の俳優が演じています。でも、メイクで誤魔化しているので、気づかない人も多いんです。
考察と感想
俳優交代の問題をメイクや撮影技術でカバーすることで、作品の一貫性を保つ努力が感じられます。視覚的なトリックを駆使することで、違和感を最小限に抑えています。
11. イライジャ・ウッドの映画デビュー
Part2の「Cafe 80’s」シーンに登場する少年、実はイライジャ・ウッドなんです!彼にとって、これが映画デビュー作となりました。
考察と感想
後に『ロード・オブ・ザ・リング』の主演を務める彼のキャリアの始まりを見ることができるのは感慨深いですね。映画の歴史を振り返る楽しみも生まれます。
12. ドクのシャツに隠された伏線
Part2でドクが着ているシャツ、よく見ると蒸気機関車と馬に乗る人の絵柄が。これは、Part3の展開を暗示していたんです。
考察と感想
衣装デザインにも伏線が仕込まれているのは、緻密なストーリー設計の証拠です。こうした細かい演出が、観客の没入感を高めています。
13. スポーツ年鑑の謎
Part2に登場するスポーツ年鑑。50年分の記録が載っているはずなのに、とても薄いですよね。実は、これはビフのポケットに入るサイズにするための映画的配慮だったんです。
考察と感想
リアリズムよりも映像としての見せ方を重視することで、物語がスムーズに進むようになっています。映画ならではの工夫の一例ですね。
14. マーティの「ママ?」
3作品を通して、マーティが気絶から目覚める時には必ず「ママ?」と言います。そして、その傍には必ずリー・トンプソン(ロレイン役)がいるんです。
考察と感想
シリーズを通じた繰り返しの演出が、映画の一体感を生み出しています。観客に「お決まりの瞬間」を与えることで、親しみやすさを強調しているとも言えます。
15. 時計台の秘密
Part1の時計台、実はユニバーサル・スタジオにあった建物を利用しています。時計部分だけを追加して撮影したんです。
考察と感想
ロケーションを活用しながら象徴的なセットを作ることで、映画の世界観が強化されています。限られた予算の中で最大の効果を生み出す手法ですね。
16. マイケル・ジャクソンとの関係
Part2の「Cafe 80’s」に、マイケル・ジャクソンのそっくりさんが登場します。実は、マイケル本人もこの映画の大ファンで、快く協力してくれたそうです。
考察と感想
ポップカルチャーの巨人が映画の世界に関与することで、よりリアルな未来像を描いています。視聴者にとっても懐かしさを感じる要素になっています。
17. 国によって変わるブランド名
Part1で、マーティの下着のブランド名が「カルバン・クライン」だと勘違いされるシーン。フランス版では「ピエール・カルダン」、スペイン版では「リーヴァイ・ストラウス」に変更されています。
考察と感想
ローカライズの工夫が、各国の観客に馴染みやすい形で映画を届ける重要なポイントになっています。文化の違いを考慮する配慮が見られます。
18. 落雷シーンの裏話
Part1のクライマックス、実は当初は核実験場でのシーンを予定していたそうです。でも、予算の都合で現在の落雷シーンに変更されました。
考察と感想
予算の制約が結果的によりドラマチックなシーンを生み出すことになったのは、映画制作の面白い点です。制約が創造力を引き出した好例と言えます。
19. ポスターアートの秘密
あの有名なポスターアート、実は公開の2週間前にやっと完成したんです。
考察と感想
映画制作の舞台裏には、ギリギリまで続く調整があることが分かります。映画の成功は、こうした細部へのこだわりの積み重ねなのですね。
20. レーガン大統領のスピーチ
Part1公開の翌年、レーガン大統領が実際のスピーチで映画のセリフを引用したんです。「Roads? Where we’re going we don’t need roads.(道路だって? 我々が向かう未来に道路は必要ない)」というセリフです。映画が現実世界に影響を与えた瞬間ですね!
考察と感想
この発言は単なる映画の引用にとどまらず、当時の政治的メッセージとも結びついています。レーガン政権は未来志向の政策を掲げていたため、このセリフが象徴的に使われたのは偶然ではなかったかもしれません。映画の影響力が政治の場にまで及ぶというのは、それだけ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が社会的に重要な作品であったことの証明でもあります。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズは名作と呼ばれますが、劇中には、アメリカの深い闇や人種差別的な表現も含まれているのをご存じでしょうか?
アメリカ映画に関する深い考察に興味がある方は、『最も危険なアメリカ映画 『國民の創世』から『バック・トゥ・ザ・フューチャー』まで』がおすすめです。

少し難しい内容も含まれますが、アメリカ映画が好きな方は一読の価値ありです。知られざるアメリカの一面を知ることができますよ!
紙の書籍なら持ち運びには不向きですが、電子書籍なら気軽にスマホでサクサク読めちゃうのでお勧めです~♪
\ 初回ログインで70%オフ! /
\『BTTF』シリーズ/
\関連記事/
まとめ
いかがでしたか? 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』には、まだまだ私たちの知らない小ネタがたくさん隠されています。これらの裏話を知ると、映画をより深く楽しめるはずです。
映画の小ネタを知ることで、単なる視聴だけでなく、新たな視点で作品を鑑賞することができます。特に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のような緻密に構成された作品では、何度観ても新しい発見があるはずです。
次にBTTFを観るときは、ぜひ今回紹介した小ネタを意識してみてください。新たな発見があるかもしれません!