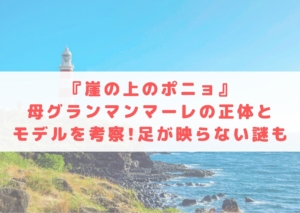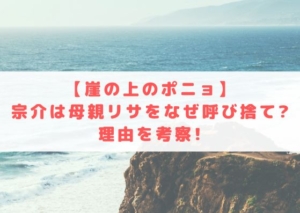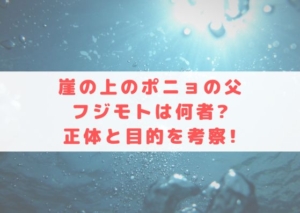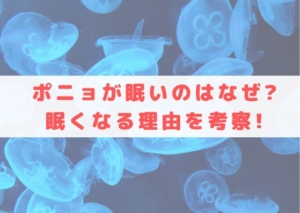映画『崖の上のポニョ』を観た人なら、一度は「ポニョってどうしてあんなにハムが好きなんだろう?」と感じたはずです。
ラーメンにハムをのせてもらって大喜びする姿は、子どもから大人まで強烈な印象を残しました。
本記事では「ポニョがハム好きなのはなぜなのか」という疑問を切り口に、作品の演出意図や文化背景、宮崎駿監督の食べ物描写へのこだわりを徹底考察していきます!
映画『崖の上のポニョ』を観て心が動かされた方には、
もおすすめです!

シネマ・コミックは、映画の美しい色彩そのままにカラーでディティールまでジブリを堪能できるコミックです。
電子書籍なら場所を取らずすぐに手元で楽しめますよ♪
\ 新規登録で70%オフクーポンもらえる! /

映画鑑賞は年間100本以上・映画ブログ運営4年
中学生の頃に『スターウォーズ』に感動して以降、
映画の沼にハマり続けて20年。
結婚・出産後も年間100本は必ず鑑賞中。
Filmarksアカウントにも鑑賞レビューを掲載中。
結論:ポニョはなぜハムが好き?(最短回答)
崖の上のポニョ
— タケシのゆっくり秘密組織🌸 (@nisigaki120) October 18, 2024
ポニョラーメン
ハムと卵が乗ってるシンプルなラーメン!
美味そう(´º﹃º`)#フォロバ100絶対 #フォローした人全員フォロバする #いいねした人フォローする #いいねした人フォロバする#いいねした人フォローして #アニメ垢フォロバ100 #アニメ好きと繫がりたい pic.twitter.com/khdZhuEtAm
結論から言えば、ハムは単なる「好物」以上の意味を持っています。
具体的には以下のような理由が考えられます。
- 子どもの無垢な欲求の象徴:素直に「食べたい!」と思える食べ物として描かれている
- 人間世界への憧れの記号:魚から人間になりたいという気持ちを“食”を通じて表現
- 海と陸の対比:海の存在であるポニョと、人間の家庭をつなぐ象徴的なアイテム
- 昭和的ごちそうイメージ:懐かしさとノスタルジーを感じさせる日本の家庭料理の象徴
つまり「ハム」は、ポニョというキャラクターの成長と世界観の対比を凝縮した小道具なのです!
作品描写から読み解く(シーン別・時系列)
日曜日に崖の上のポニョを見た後、チキンラーメンにハムとか卵乗っけたやつお昼に出したら、👦「オイチイ、オイチイ…!」と食べていた。美味しいよねジブリ飯。
— 長谷川ちひろ (@mogimogi_) March 4, 2025
(画像は拾いもん) pic.twitter.com/iV5JbtA9Pw
宗介の家の台所シーン
7.11 ラーメンの日🍜🍥
— せやかて工藤 (@zxun72) July 11, 2024
『崖の上のポニョ』
魚の女の子と人間の男の子の交流を描いたアニメ。リサさんのハムラーメンが家庭的で美味しそうだった。基本子ども向けで可愛らしい作品なんだけど、時折ドキッとする恐ろしい展開もあって印象に残ってる。歌よく流れてたなあ。ポーニョポーニョポニョ pic.twitter.com/AQas117akf
嵐の翌朝、宗介とポニョがインスタントラーメンを作って食べる場面。
宗介の母・リサがハムをのせてくれた瞬間、ポニョは目を輝かせて大喜びします。
この一連のシーンは「ハム=ごちそう」として強烈に印象付けられました。
「ハムちょうだい!」の台詞と表情
理想のサンドイッチは崖の上のポニョでリサが作ってたサンドイッチかもな〜✨
— 毎日ペペロンチーノ (@mai__pepe) March 13, 2024
ポニョにハム食べられてまうけどね笑 #hapimoni #jfn pic.twitter.com/Yk93JRTqYO
無邪気な声と表情で「ハムちょうだい!」と訴えるポニョの姿は、観客に強い共感と可愛らしさを残しました。
セリフの響きやテンポも印象的で、SNSやミームで繰り返し引用され続ける理由のひとつです。
変身段階と食の描写の連動
📺今宵の映画番組🍿
— 映画.com (@eigacom) August 21, 2025
「崖の上のポニョ」
▶https://t.co/JzSuOTYnpv
🐟今夜9時 #金曜ロードショー で放送❗️
宮崎駿監督が手がけた長編アニメーション✨人間になりたいと願うさかなの女の子・ポニョと、心優しい5歳の少年・宗介の交流と冒険を描いたファンタジーです🪼🚢🍜🫙@kinro_ntv pic.twitter.com/OLzM7y7DYW
魚から半人半魚、そして人間へと変化するポニョ。
その過程で「人間の食べ物」を喜んで食べる描写は、彼女の変身と成長のシンボルになっています。
フジモト/グランマンマーレの視点
◎本日、8月8日は天海祐希さんのお誕生日です。
— ジブリのせかい【非公式ファンサイト】 (@ghibli_world) August 8, 2024
天海さんは、『崖の上のポニョ』でグランマンマーレを演じています。
✨🎂HAPPY BIRTHDAY🎂✨ pic.twitter.com/oYVIKa8My9
ポニョの両親的存在であるフジモトやグランマンマーレからすれば、人間の食べ物に惹かれることは「異世界に足を踏み入れる」行為。
ここにも“海と陸の境界”をテーマとする物語の一貫性が見られます。
制作意図の考察:宮崎駿の“食べ物演出主義”
ジブリの食べ物より
— 無 (@Kei130608) August 10, 2018
食欲そそられるものはない。
1枚目・ハウルの動く城
(ベーコンエッグ)
2枚目・崖の上のポニョ
(ラーメン)
3枚目・魔女の宅急便
(カボチャとニシンのパイ)
4枚目・千と千尋の神隠し
(バーワン他)#ジブリ #共感してくれる人RT #いいね pic.twitter.com/vAs055uNVh
ジブリにおける食事シーンの役割
宮崎駿の言葉
— アマデウス (@GyyARm5pyYHddh0) August 17, 2025
いまのような、どこに自分たちが行くんだろうと、自分で考えないとわからない時代が来たときに、歴史的なことに対する無知とかいうのはいずれしっぺ返しが来る pic.twitter.com/WIJqC2edqb
宮崎駿監督は「食べ物をおいしそうに描く」ことを重視しており、それは登場人物同士の距離を縮め、観客の共感を呼ぶための重要な演出です。
ポニョのハム好きも、この方針の延長にあるといえるでしょう。
小道具としてのハムの効果
ハムといえば……
— しろ (@shiro710) August 6, 2020
崖の上のポニョのラーメン
チキンラーメンに
ハム、ゆで卵、ネギをトッピング
ごま油をたらして完成
#あつまれ飯テロの盛り#ハムの日 pic.twitter.com/ezZcamKRLz
- 形:丸い薄切りで描きやすく、アニメでも一目でわかる
- 色:赤系のピンクがポニョのキャラクターカラーと調和
- 動き:重ねたり浮かべたりでき、画面演出に多彩さを与える
色彩設計との調和
崖の上のポニョ🩵金曜よる9時
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) August 18, 2025
好奇心旺盛で元気なさかなの女の子・ポニョ🐟
5歳の男の子・宗介に危ないところを助けられ人間になりたいと願うように… pic.twitter.com/dxHDOWWywW
赤いポニョとピンクのハムが同じ画面に映ることで、映像としての統一感や可愛らしさが増しています。
日本の食文化・時代背景とハム
ジブリ飯再現
— 七草 粥(ななくさ かゆ) (@tyubasa001) December 7, 2023
第4弾
崖の上のポニョより
「リサのハムラーメン」
作中でポニョがハムを美味しそうに食べたあと、ウトウト( ¯꒳¯ )ᐝするシーンが可愛いですね( * ֦ơωơ֦)
ベースはチキンラーメンで、具を乗せるだけのお手軽さ!
チキンラーメンが嫌いでなければ食べてみてね♪#ジブリ飯再現味優先 pic.twitter.com/XQ268GfPqX
昭和の家庭におけるハムの位置づけ
戦後から昭和にかけて、ハムは「家庭のごちそう」でした。
給食やお弁当の定番でもあり、子どもが憧れる存在でもあったのです。
子ども目線の“特別なおかず”
当時の子どもにとって、ハムは日常と非日常の境目にある“ごちそう”。
ポニョが見たときの輝く瞳は、その感覚を象徴しているともいえます。
保存性と非常時食
嵐の中でラーメンにハムをのせるシーンは、保存性のある食材としての側面も暗示。
非常時でも“ちょっと贅沢”を演出できる食材としてリアリティを持っています。
よくある疑問に先回り
【#ジブリ】今夜金曜ロードSHOW「崖の上のポニョ」結局あれなんなの? 疑問解決Q&A http://t.co/FYUQNc2ut3 pic.twitter.com/8MkgaZ2nuC
— エキサイトニュース (@ExciteJapan) February 13, 2015
ラーメンの具がハムなのはなぜ?
チャーシューやベーコンでもなく「ハム」なのは、子どもが直感的に喜ぶ食材であり、色彩・形のわかりやすさも理由のひとつと考えられます。
ハムは何枚のっていた?
描写ではラーメンに2枚ほどのっています。量よりも「特別感」を出すことが優先されていると解釈できます。
もしハム以外だったら?
卵やチーズなども候補になり得ましたが、赤系の色合いや描きやすさを考えると「ハム」が最適解だったといえるでしょう。
ハムの種類や銘柄は?
作中で具体的なブランドや種類は示されていません。むしろ「誰もが知っている定番のハム」として描かれることで、普遍性を強めています。
他作品との比較でわかる「食」の役割
気づけばジブリ食べ物絵が4枚以上になってたのでまとめ たぶんまだ描く pic.twitter.com/HFiuG2O7AW
— めりはり (@me_ri_ha_ri0) December 10, 2023
- 『となりのトトロ』:トウモロコシ=病気の母への贈り物と癒し
- 『天空の城ラピュタ』:パン+目玉焼き=冒険と友情のエネルギー
- 『魔女の宅急便』:ニシンとかぼちゃのパイ=共同体とのつながり
- 『千と千尋の神隠し』:境界を越える食=人間と異世界をつなぐ儀式
ジブリ作品では食べ物が物語の重要な要素を象徴します。『崖の上のポニョ』のハムもその系譜に連なる存在です。
観客の記憶に残る理由(心理・メディア論)
海苔さん!(@_noritoto_ )
— 藤田フジ (@fda1900) December 7, 2018
崖の上のポニョ
あの、ポニョポニョしててかわいいなって…おも…思ってて…!!かわいいです!!!!!!!!😭😭🙏🙏✨✨ pic.twitter.com/QBr2fwVmN9
- シンプルで分かりやすい:誰でも知っている食材だから記憶に残る
- 強烈な可愛らしさ:「ハムちょうだい!」の台詞が耳に残る
- 拡散力の高さ:SNSや動画で切り抜かれ、ミームとして定着
これらの要素が組み合わさり、「ポニョ=ハム好き」という文化的イメージが広まりました。
視聴ガイド(ネタバレ最小で楽しむために)
「崖の上のポニョ」のラーメンみたいで美味しそう☺ pic.twitter.com/TdYjktw48L
— yossy (@yossh10) March 18, 2023
- 初見の方は「ポニョがハムを見た瞬間の反応」に注目
- 見返す際は「ポニョの変身段階と食の描写の関係」を観察
- 親子で観る場合は「自分なら何をラーメンにのせたいか?」と話すと楽しい会話が生まれます
映画『崖の上のポニョ』を観て心が動かされた方には、
もおすすめです!

シネマ・コミックは、映画の美しい色彩そのままにカラーでディティールまでジブリを堪能できるコミックです。
電子書籍なら場所を取らずすぐに手元で楽しめますよ♪
\ 新規登録で70%オフクーポンもらえる! /
\『崖の上のポニョ』関連記事/
まとめ:ポニョとハムが教えてくれること
/22の金曜ロードショーは夏のジブリ特集第2弾、2008年の「崖の上のポニョ」が放送されます。17年前の作品ですね~!
— たいちゃん (@TAIKI_199086) August 21, 2025
さかなの子・ポニョと人間の宗介との心温まる物語です。録画では所有していませんが内容は大体、知ってるので録画はスルーします。 pic.twitter.com/fo0xqyMXUA
『崖の上のポニョ』に登場する「ハム」は、単なる食べ物ではありません。
子どもの無邪気さ、人間世界への憧れ、海と陸の対比、そして日本の食文化までを象徴する多層的なアイテムでした。
- 子どもの“好き”を体現するハム
- 人間世界への憧れを表す象徴
- 作品世界における海と陸のコントラストを補強
- 昭和的な家庭のごちそうとしてのノスタルジー
だからこそ、観客は「あのハムのシーン」を忘れず、今も語り継いでいるのです!
あなたは「ポニョがなぜハムを好きだったのか」、どんなふうに感じましたか?
再び映画を見返すと、きっと新しい発見があるはずです。