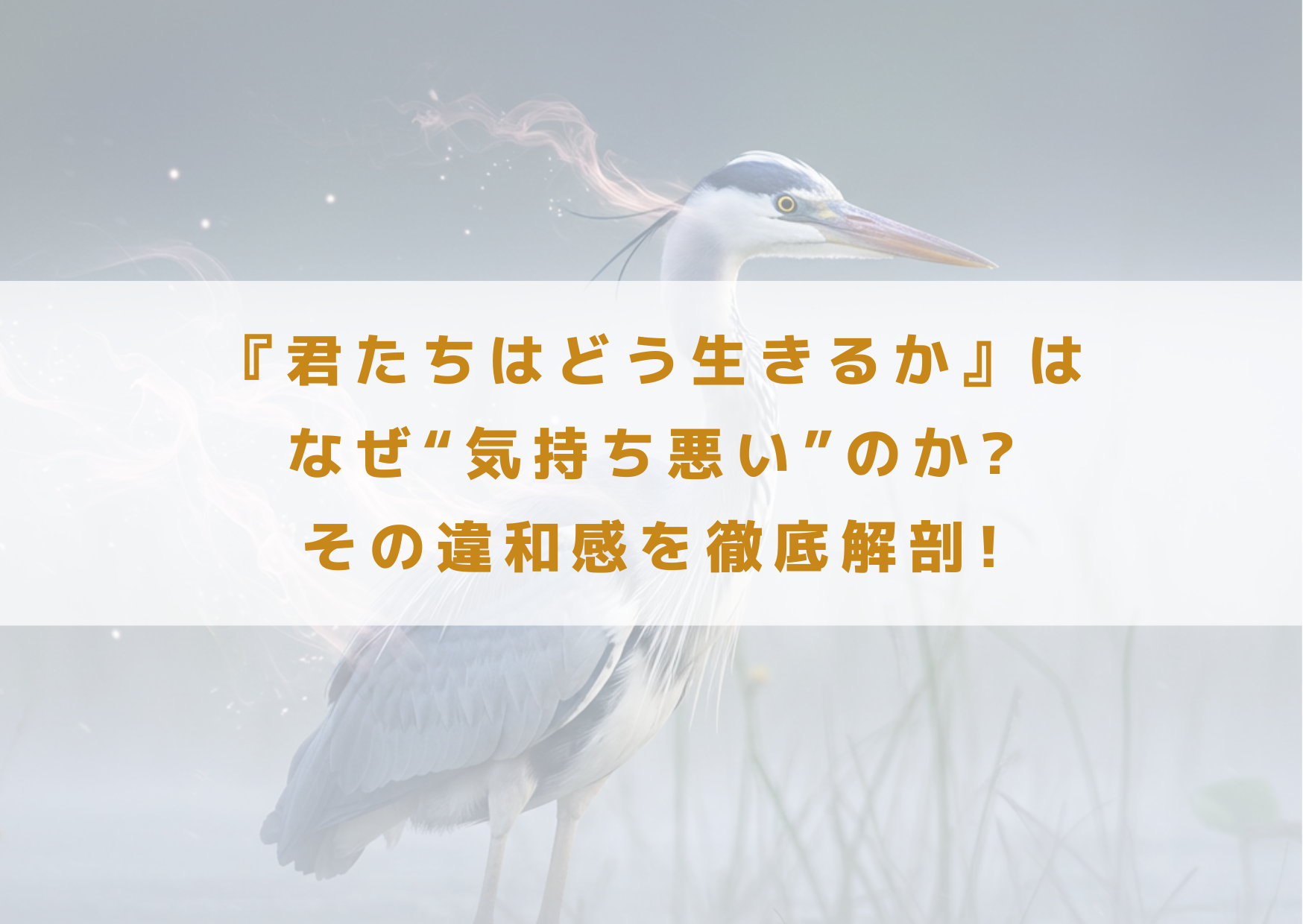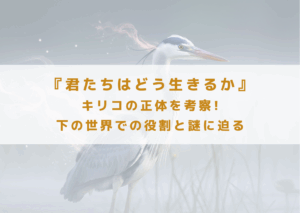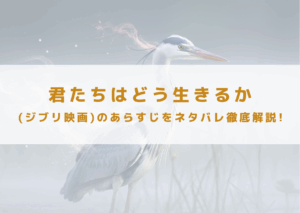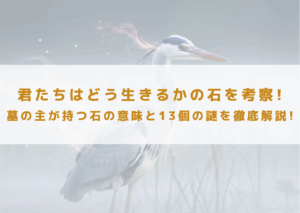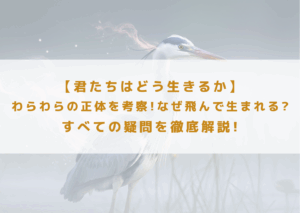『君たちはどう生きるか』というタイトルは、かつての名著を思わせる響きを持ちながらも、宮崎駿が描いた最新作では全く異なるアプローチで観客に問いを投げかけます。
映画の内容や演出には強いインパクトがあり、多くの人が「気持ち悪い」と感じたとSNSやレビューで声を上げています。その感覚は一過性のものではなく、視覚的、心理的、構造的な要素が複雑に絡み合った結果として生まれているのです。
この作品が引き起こす「気持ち悪さ」とは何か。それは単なるグロテスクな描写や理解しづらい物語構成だけではありません。そこには、私たち自身が見たくない「内面の不安」や「社会の違和感」が巧妙に織り込まれているのです。
本記事では、その違和感の正体を多角的に掘り下げながら、なぜこの作品が賛否両論を巻き起こすのかを探っていきます。
ジブリの映画『君たちはどう生きるか』を観ると、元ネタの『君たちはどう生きるか』も気になってきますね!内容はかなり違いますが、映画がインスピレーションを受けたのは間違いないようです!

漫画版が読みやすいのでお勧めです!
本で所有しているとちょっと重いし場所も取りますが、電子書籍なら気軽にサクサク読めちゃいます♪
\ 新規登録で70%オフクーポンもらえる! /

映画鑑賞は年間100本以上・映画ブログ運営4年
中学生の頃に『スターウォーズ』に感動して以降、
映画の沼にハマり続けて20年。
結婚・出産後も年間100本は必ず鑑賞中。
Filmarksアカウントにも鑑賞レビューを掲載中。
気持ち悪い要因①視覚的な不快感
「君たちはどう生きるか」を検索したら「気持ち悪い」って出てきたんだけどどうして pic.twitter.com/QrwQG1Gocj
— スカポン (@RoLLING_SU_qa) July 13, 2023
キャラクター造形が異形すぎる
宮崎 駿氏によるアオサギのイメージボードを使用! 「SWITCH Vol.41 No.9」の表紙が公開 「君たちはどう生きるか」の制作スタッフインタビューを掲載 https://t.co/O6oM058zMg #君たちはどう生きるか pic.twitter.com/Fg9QrdUe50
— GAME Watch (@game_watch) August 18, 2023
物語の中核を担うアオサギは、もはや鳥の範疇を超えた存在です。
異様に長い首、歯のある口元、人間のように喋る知性――これらが生み出すのは、単なる「気持ち悪さ」ではなく、人間の本能的な嫌悪を呼び起こすデザインです。
観る者は「これは何だ?」という困惑を突きつけられます!
人間と動物の境界を曖昧にするキャラクターたち――例えば人食いインコの軍団や、ぬめぬめした謎の生物――も同様です。こうした存在は、
“異界”の不安定さや、主人公眞人の内面世界の歪みを
視覚的に体現しています。
視覚的なグロテスクさが「異質」への拒否反応を引き出し、
それが「気持ち悪い」と形容される要因となっている
と考えられます。
さらに注目すべきは、これらのキャラクターの動きや音もまた、違和感を増幅させる仕掛けになっていることです。
わざと人間に似せているようで、決して同化しない微妙な不一致。そうした“境界の歪み”が、観客の無意識にある安心感をじわじわと揺さぶるのです。独特の表現なので、映画を観ている最中、終始なんだか気持ち悪さを感じます。
演出がグロテスクすぎる
君たちはどう生きるか見てきた。ほぼ何かのメタファーで描かれるパプリカだったけどアーティスティックで割と好きなお話だった。82歳に見えてる世界凄い。てかそう抽象化しないと権威と無神経さに振り回されるかなりグロい話しになる気もする笑 pic.twitter.com/EHV0KBrMrV
— onoken | owl*tree (@ax_onoken) July 19, 2023
巨大な魚の解体、カエルの大群、血を流すシーン…。
宮崎作品にしては珍しく、直接的なグロテスク表現が多く含まれています。
しかしこれは、単なる視覚的ショックを狙ったものではありません。
眞人が感じている「死」「喪失」「不安」の感覚を、
観客に皮膚感覚で追体験させるための演出
と読み取れます。
特に、解体のシーンや血の表現は、観る側の「生理的嫌悪感」を意図的に引き起こしています。これはショックのためではなく、
主人公と同じ地平に観客を引きずり込むための装置であり、
物語を“眺める”のではなく、“一緒に感じる”ための演出
なのです。
その不快感は、物語と観客を分断するのではなく、むしろ強く接続するための導線として機能していると言えるでしょう。観客はわざと「気持ち悪さ」を感じさせられていたのですね。宮崎駿監督、恐るべしです。
“不快”のデザイン:鳥、魚、カエルたちの象徴性
多分だけど君たちはどう生きるか見てる_(:3 」∠)_カエルが大量に出て来た pic.twitter.com/AmRJLKy45D
— Sui🐱🍣_(:3 ⌒" )_ (@sk_suip) January 30, 2025
アオサギが象徴するのは死と再生。魚は“生”の象徴であると同時に、食と暴力の結びつき。カエルは集団性や異質なものの侵入。
これらが不快であるのは、私たちが無意識に回避しようとする“生の根源的な現実”を突きつけてくるからです。
そして
これらのモチーフは、単に「グロい」「不気味」なだけではなく、主人公の精神状態の投影でもあります。
アオサギは“呼びかける死者”、カエルは“圧迫する社会性”、魚は“変質する命”のメタファーと読むこともできるのです。
宮崎監督がかつてないほど明示的に“気持ち悪い”演出に踏み込んだのは、それだけ眞人の物語が“人間の奥底”に踏み込んでいるからに他なりません。
気持ち悪い要因②ストーリー構造と心理的不安
「君たちはどう生きるか」
— アカメ (@akame62) July 19, 2023
情報皆無に等しい状態だったので、鑑賞中びっくりするくらい期待と不安で胸がいっぱいになってしまった
事前情報無しの威力ってすごい pic.twitter.com/TnS9rECcaA
難解で抽象的な物語展開が生むモヤモヤ
本作の物語は、現実と異世界を行き来することで構成されており、直線的なストーリー展開とは一線を画します。
眞人の主観を軸に描かれるため、夢か現か判然としない場面が多く、物語の筋を追うこと自体に困難が伴います。
この「曖昧さ」が観客に解釈の自由を与えると同時に、「意味がわからない」「よく分からなかった」というフラストレーションも生み出してしまうのです。
このような構造は、死者の世界への旅や、少年の心の成長を寓意として描く一方で、観る人の内面と向き合う時間を要求します。
眞人の旅が現実逃避ではなく、現実との対峙であると気づいたとき、観客もまた自身の内面を旅することになるのです。
この過程が難解で不親切に映る一方で、それこそが作品の本質であるともいえるでしょう。
登場人物への感情移入の難しさとその意義
#おまえら何言ってんだこの映画は良いだろ
— snob (@iimsnob) July 11, 2024
「君たちはどう生きるか」
確かに難しい作品だったけど
ジブリ最新作観れただけ幸せです pic.twitter.com/xkSTXRs7Jv
『君たちはどう生きるか』では、登場人物たちの内面が台詞で語られることはほとんどありません。主人公の眞人ですら、その行動原理や心理描写は抑えられており、彼の苦しみや葛藤は表情や沈黙、そして行動によってのみ語られます。
これにより、
観客は眞人の心情を読み取ることに苦労し、「感情移入が難しい」と感じる
ことになります。
しかし、そこにこそ宮崎監督の狙いがあります。
私たちは他者の心を完全には理解できない——だからこそ、相手の立場に立って想像する必要があるのだと。
この作品では、言葉では語られない部分を観る者が補うことで、物語が“受動的に理解する”ものではなく、“能動的に体験する”ものへと変化していきます。
その体験のなかで、「気持ち悪さ」が内面の鏡となるのです。
「眞人の自傷」や「義母との関係」に見られる不協和音
『君たちはどう生きるか』。自分への攻撃性(石での自傷行為)と他者への攻撃性(弓矢作り)が、母親からプレゼントされた本を読むことで、物語と向き合う勇気に変わるシーン。理想の読書体験を描いたこの映画は、読書感想文の季節にピッタリです! pic.twitter.com/qTPFJZGHck
— Hiroki Shimazaki (@hi_loki_0x0p) August 8, 2023
特に議論を呼んだのが、眞人が自らの頭を石で打つ自傷行為のシーンです。この突発的な行動は、母の死、父の再婚、そして新しい家庭に対する怒りや絶望が一気に爆発した結果だと推察できます。
しかし、その背景や心理状態が物語上で十分に説明されないため、観客は戸惑い、恐怖や違和感を覚えるのです。
また、義母となった夏子に対して眞人が抱く複雑な感情も丁寧には描かれません。
急な再婚、夏子の妊娠、無理やり新しい生活を受け入れさせられる状況は、戦時下の日本のリアルを反映しつつも、現代の観客にとっては倫理的な違和感を引き起こします。
この
“説明不足”と“現代的な感覚のずれ”が重なることで、「家族が気持ち悪い」「大人たちに共感できない」といった感情が生じる
のです。
気持ち悪い要因③観客を試すような演出とメディア戦略
君たちはどう生きるか、見た!!
— フッキー (@fxxky_71) July 14, 2023
マーケティング的にどうこう置いておいて、何にも見ずに行ってほしいから俺はこれでよかった!!!数年ぶりに観たジブリは、俺が子供の時に観たジブリそのものだった pic.twitter.com/SiwVdHvoJ3
意図的な情報遮断による混乱と期待の裏切り
ジブリ史上前例のないマーケティング手法として、『君たちはどう生きるか』は事前のプロモーションを徹底的に制限しました。ポスターにはタイトルと鳥のビジュアルのみ、予告編も情報解禁もほぼゼロ。
これによって、「一体どんな映画なのか?」という期待と興味を喚起する一方、観客側に過度な想像と理想化を生んでしまう結果にもつながりました。
結果として、
観客が抱いていた「ジブリ的な感動物語」や「癒しのファンタジー」とはかけ離れた内容に、強い違和感を感じた
という声が続出します。
この「情報遮断」という戦略そのものが、映画の主題である“不確かな世界”“見えないものと向き合うこと”とリンクしているとも解釈できますが、それを理解する前に“騙された”と感じた人も少なくなかったのです。
さらに、この情報遮断によって観客はほぼ“白紙の状態”で鑑賞に臨むことになり、説明不足のまま物語に放り込まれる感覚を受けたという声も多く聞かれました。
これは、観客自身が眞人のように不安や混乱を抱えながら“旅をする”という体験を促す構造でもあり、ある意味で観る者が試される設計になっていたのです。
「ジブリらしさ」とのギャップがもたらすショック
📖『千と千尋の神隠し』絵コンテ全集
— イイ映画🎬@シネマフロントライン (@E_eiga) April 21, 2025
スタジオジブリを代表する名作 『千と千尋の神隠し』 📽️
その制作過程を 宮崎駿監督自らの絵コンテ で完全収録!
映画の すべてのシーンが絵コンテで見られる 貴重な一冊。
映像では一瞬で過ぎるシーンも、宮崎監督の細かな描写と指示が伝わる✨… pic.twitter.com/CCnXbo74hc
過去のジブリ作品、たとえば『となりのトトロ』や『魔女の宅急便』、『千と千尋の神隠し』といった名作群は、子供でも楽しめる明るさや、明確な感情の起伏、視覚的な美しさが共通していました。
観客が“ジブリ=安心できる物語”という先入観を持っていたことは想像に難くありません。
しかし
今作は、それらの「ジブリらしさ」を意図的に裏切るような作りになっており、優しく包み込むような展開ではなく、見る者の“心の深部”に触れるような不安定さを持ち込んできます。
このギャップが「ジブリにこんな作品を求めていなかった」と感じさせ、「気持ち悪い」「不快だった」といった評価に繋がっているのです。
また、視覚的な描写だけでなく、ストーリー構造や登場人物の描き方も従来のジブリ作品とは明確に異なります。
感情的なカタルシスが用意されていないため、「見終わってもスッキリしない」「どこか居心地が悪い」という反応が出るのは、まさに“ギャップ”が引き起こした副作用と言えるでしょう。
売り出し方が作中テーマと噛み合わない違和感
珍しく妻と見たい映画が一致したので二人で『君たちはどう生きるか』
— 薙澤なお (@nagisawanao) July 18, 2023
見てきました✨
結構前、青さぎを町中で見かけたとき物凄く違和感を覚えたことがありましたが、そんな不思議な感覚が沢山つまっていた、とても宮﨑駿監督最後の作品❔とは思えないエネルギー溢れる作品だった👀 pic.twitter.com/Vs5JidytYt
小説版『君たちはどう生きるか』は、「人生を変える一冊」「中高生必読の教養本」として紹介されてきました。
その延長線上でこの映画を受け止めようとした人にとっては、抽象的で難解な映像表現、グロテスクで不気味な描写、そして結末の曖昧さは、期待していた内容とまるで異なっていたのではないでしょうか。
つまり、「売り方」と「中身」にギャップがあり、その違和感が“気持ち悪い”という感想を助長した側面も否定できません。
宣伝では哲学的なメッセージ性を強調しつつ、実際の映像体験は非常に感覚的で、物語の筋を掴みづらい。この落差が、観る側にとって一種の“裏切り”と感じられてしまったのです。
同時に、映画の中で問いかけられる「生き方」というテーマは、観客の年齢や経験によっても大きく感じ方が異なります。
年齢が若い人ほど説明のなさに戸惑い、年齢を重ねた人ほどその曖昧さに含みを感じる。マーケティングの対象が広すぎたことも、違和感の一因といえるでしょう。
「気持ち悪い」の本質と向き合う
今日は気分転換にちょっとお出かけして来た🚶♀️焼肉ランチを食べて優待消費に君たちはどう生きるかを見たよ🎬
— ぬぅ (@gnu7777) July 26, 2023
鳥の苦手な人はちょっと気持ち悪いかもって聞いてたけど、蛙の方がうへぇ〜となりました🐸
今までのジブリ詰め合わせ感が凄かったな〜 (*>ω<)ω<*)ぎゅ〜♡ pic.twitter.com/cMPPyt6MUH
観客自身の“心の奥”をえぐる構造
『君たちはどう生きるか』が多くの人に「気持ち悪い」と感じさせる理由は、映像や物語の表層だけでは説明しきれません。実際には、
観客一人ひとりの内面に潜む不安やトラウマ、社会的な違和感に直接触れるような演出が施されており、その“内面を突く感覚”こそが真の違和感を生んでいる
と思われます。
宮崎駿監督はこれまでも『もののけ姫』や『千と千尋の神隠し』などで「自然と文明の対立」や「成長の痛み」を描いてきましたが、今作ではより踏み込んだ形で“観客の心理そのもの”にアプローチしています。
ストーリー上の違和感や不快感は、単に演出上の仕掛けではなく、「あなた自身はこの世界にどう向き合うのか?」という問いを突きつける装置なのです。
つまり、“気持ち悪い”と感じるのは、
作品の中にある何かが「自分の中にもある」と直感的に理解してしまうから。
それは過去の喪失体験かもしれないし、社会に対する不信かもしれません。その“自覚したくない感情”を炙り出された時、人は「これは気持ち悪い」と口にするのです。
「君たちはどう生きるか」という問いかけの強さ
午前10時前から、スタジオジブリの新作映画「君たちはどう生きるか」を鑑賞。
— 大村秀章 (@ohmura_hideaki) July 29, 2023
戦時中、そして謎のアオサギに導かれた異世界を通じて、主人公の少年・眞人が火災で失った母を一途に想う姿が描かれ、宮﨑駿監督からの今この世界をどう生きていくかという問いかけやジブリの世界観が詰まった名作でした! pic.twitter.com/PDzrSLKO2t
本作のタイトルそのものが、観客に強く作用しています。「君たちはどう生きるか?」という一文は、他人事ではなく、まっすぐに個人の生き方に関わる問いです。
映画の中で明確な答えが提示されるわけではなく、むしろ謎が謎のまま残されることで、観客自身にその問いを返してくるのです。
この問いかけは、実は非常に暴力的です。
私たちは普段、誰かに「どう生きるべきか」と問われることなく生きていますが、本作ではその逃げ場のない命題を突きつけられます。観終わった後の「モヤモヤ」や「ざらつき」は、その問いに正面から向き合おうとした痕跡とも言えるでしょう。
さらに、この問いには“他者との関係性”が潜んでいます。
眞人が出会うキャラクターたちは、皆どこか未完で、自己のアイデンティティを探している存在です。
彼らとの対話を通じて、観客自身もまた「自分はどう在りたいのか」と、これまで考えなかった視点から自分を見直すことになるのです。
不快感が残るからこそ生まれる“余韻”という価値
先週末ついに観れてまだ余韻に浸ってます、君たちはどう生きるか❗️ pic.twitter.com/aYiz0F9KXd
— 角野未来 (@miraisumino) November 23, 2023
エンタメ作品の多くは、観終わったときに“スッキリ”したり、“感動”したりする構造が仕込まれています。しかし本作では、
わざと“未解決感”を残すことで、観客の思考を止めない工夫
がなされています。
それが「気持ち悪さ」の正体であり、同時に“余韻”という名の価値でもあるのです。
この余韻は、一見ネガティブに感じられるかもしれません。
しかし、それは観る者の心に長く残り、時に日常の中でふと立ち止まる瞬間を生み出します。「自分は今、どう生きているのか?」と。つまり、
ジブリの映画『君たちはどう生きるか』を観ると、元ネタの『君たちはどう生きるか』も気になってきますね!内容はかなり違いますが、映画がインスピレーションを受けたのは間違いないようです!

漫画版が読みやすいのでお勧めです!
本で所有しているとちょっと重いし場所も取りますが、電子書籍なら気軽にサクサク読めちゃいます♪
\ 新規登録で70%オフクーポンもらえる! /
\『君たちはどう生きるか』/
\関連記事/
まとめ:なぜ「気持ち悪い」と感じたのかを自分に問う
家にあった #吉野源三郎 の #君たちはどう生きるか を読んでみた。小説と映画は関係ないとはいえ、コペル君と眞人君は境遇も考え方も重なる部分が多いにあって、君たちはどう生きるかの問いが清々しいラストだった。ここで #地球儀 流れてもおかしくない!コペルニクスからついたあだ名だし🌍🪐 pic.twitter.com/u1es9VI0cS
— 米は玄米 (@come_wa_genmai) August 23, 2023
3つの視点で整理する『気持ち悪さ』の正体
- 視覚的ショック:異様なキャラクターとグロテスクな表現が本能的嫌悪を誘う
- 心理的違和感:キャラクターや物語に共感しづらい設計が心の深部を刺激する
- 構造的な挑発:未解決のまま投げかけられる「生き方」の問いが観客に突き刺さる
これらは全て“偶然”ではなく、宮崎駿が明確な意図を持って構築したものです。
だからこそ「気持ち悪い」と感じたとき、その正体を見極めることで、作品の本質が見えてくるのです。
違和感は拒絶ではなく“問い”の入り口
映画に違和感を覚えることは、決して“失敗”ではありません。
むしろ、
それは作品が観客の思考や感情に“届いた”証拠です。『君たちはどう生きるか』の違和感とは、あなた自身の人生と向き合うための入り口であり、拒絶ではなく“探求”の始まりなのです。
それをきっかけに他者と語り合い、自分の過去や価値観を見つめ直すことで、この作品が残した“問い”は意味を持ち始めます。
違和感はそのままにせず、ぜひあなたの中で“育てて”みてください。
もう一度観ることで見えてくる“生き方”のヒント
初見では理解できなかったことも、二度目、三度目の視聴で腑に落ちることがあります。
それは単にストーリーを理解するという意味ではなく、「今の自分がどう生きているか」という感覚と共鳴し、視点が変わることによる発見です。
『君たちはどう生きるか』は、観る者の年齢、経験、心境によってまったく違う顔を見せる映画です。
一度きりの鑑賞で終わらせず、人生の節目節目で見返してみてください。きっと、その“気持ち悪さ”の向こうに、あなたなりの“答え”が見えてくるはずです。