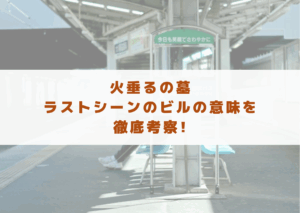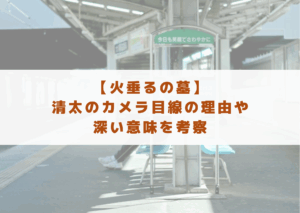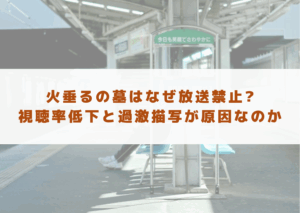映画『侍タイムスリッパー』というタイトルを見て、「あれ?時代劇なのに舞台は現代?」「それとも幕末?」と混乱する方も多いのではないでしょうか。
本作は、“幕末の侍が現代京都にタイムスリップして第二の人生を歩む”という異色の物語。
この記事では、「侍タイムスリッパー」の時代設定に注目し、なぜ2007年の現代を舞台としたのか、その理由と意味、そして物語全体に与える効果までを深掘りして解説します。

映画鑑賞は年間100本以上・映画ブログ運営4年
中学生の頃に『スターウォーズ』に感動して以降、
映画の沼にハマり続けて20年。
結婚・出産後も年間100本は必ず鑑賞中。
Filmarksアカウントにも鑑賞レビューを掲載中。
『侍タイムスリッパー』の時代設定はいつ?
『侍タイムスリッパ―』アマプラでみたよ~
— にっしん (@NIS_41) June 1, 2025
面白かった!寺のおばちゃんがめっちゃ好き
現代時代劇もっと観たいな pic.twitter.com/ip3sDo8CyP
幕末と現代――ふたつの時代をまたぐ物語構造
物語は、幕末の京都を生きる武士・高坂新左衛門が、ある密命の最中に落雷に遭い、現代(2007年)の京都へとタイムスリップするところから始まります。
目を覚ました彼がいたのは、まさかの“時代劇撮影所”。
ここで彼は、本物の侍として「斬られ役」を演じることになっていきます。
このように、本作の時代設定は大きく「幕末」と「2007年の現代」の2軸で構成されています。
単なるタイムスリップものにとどまらず、時間を超えた価値観の衝突と融合が描かれています。
現代パートの具体的な年は2007年!その意味とは?
話題の侍タイムスリッパ―鑑賞。
— 女子ゴルファー大図鑑 管理人 (@go_go_joshigolf) October 13, 2024
①タッチパネルの購入方法わからず係員に逆切れしてる老害発見
②ヒロインが『看護婦』、じじいが『看護師』ってセリフで言ってたけど感覚的には逆の方が良かったような…ってかガラケー使ってる時代なら共に看護婦でも…
③笑いがベタで古い。
期待ほどでは…まずまず pic.twitter.com/TRgodnDq0C
本作で特筆すべきは、“現代”が2020年代や令和ではなく、2007年に設定されていることです。
これは単なるノスタルジーではありません。
2007年という年は、ガラケーやビデオカメラがまだ活躍し、時代劇撮影所も日常的に機能していた“ギリギリ時代劇文化が生活に根ざしていた時代”。
その選択によって、物語は現実味を持ち、同時に時代の変化を象徴的に描き出すことに成功しています。
なぜあえて現代が舞台なのか?
『侍タイムスリッパ―』
— ポーリア@ (@bH5f4ZFQgMIrSyg) September 23, 2024
140年後にタイムスリップした侍。
現代の京都の時代劇撮影所へ。
その驚きはどれほどのものだったでしょうか?
それでもかつての会津藩士の高坂新左衛門は、自分が与えられた仕事に懸命に取り組みます。
彼の真摯な姿は観客の心を打つ美しさを持っていました。 pic.twitter.com/Fz9s1vcbpT
現代京都×幕末侍――「時代劇の終焉と再生」を描く狙い
『侍タイムスリッパー』の主舞台は、京都にある時代劇撮影所。
高坂が目を覚ますこの場所こそ、「時代劇」が作られる現代の現場。
彼が“本物の侍”であるという皮肉な設定により、観客は「本物と作り物の境界」「時代劇とは何か」という本質に自然と向き合うことになります。
本物の侍が現代で生きる意味と物語性
地上波初放送#侍タイムスリッパー
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) July 16, 2025
金曜よる9時
時は幕末…
会津藩士の高坂新左衛門が長州藩の男と刃を交えたその時、突然雷が鳴り響き気を失ってしまう⚡️
目を覚ますと…そこは現代の時代劇撮影所だった!!#侍タイ pic.twitter.com/lh0FVYW7Ul
高坂は、かつて命を懸けて戦っていた“侍”という存在。しかし現代では、侍はただのエンタメコンテンツでしかない存在。
そのギャップがもたらす滑稽さと哀しみ、そして彼が現代人と出会い、改めて“生きる意味”を見出していく過程は、人間ドラマとして深い感動を呼び起こします。
タイムスリップという設定が、侍の精神性と現代社会の空虚さを対比する装置として極めて有効に機能しているのです。
2007年を選んだ理由:ノスタルジーとリアリティの交差点
2007年は、次のような特徴を持つ絶妙な時代です:
- スマホ前夜。ガラケー文化やアナログ的な生活感が色濃く残る
- 時代劇撮影所がまだ元気だった(撮影所の稼働率・雰囲気)
- 映画やテレビの“時代劇文化”が辛うじて市民権を持っていた
- SNSがまだ広く普及しておらず、情報のスピードも緩やかだった
この時代を選ぶことで、現代社会の喧騒やデジタル疲労から一歩引いた「静かなリアリティ」が演出されており、時代劇との親和性が非常に高くなっています。
時代設定が物語にもたらす影響とは?
『侍タイムスリッパ―』アマプラにて劇場以来の再鑑賞。
— タバスコ(7割) (@Tabasukorider) March 22, 2025
何回観ても楽しい映画😊
激動の時代を生きた侍をリスペクトし、廃れゆく時代劇を応援し、良くできたコメディでもある。
「最後に武士」二人の姿勢の良さにも惚れました。
ラストはやっぱり泣いちゃいましたね。
心配無用の介ドラマ化希望! pic.twitter.com/GHmF0zHImC
コメディとドラマの融合を可能にした「時代設定」
地上波初放送#侍タイムスリッパー
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) July 14, 2025
金曜よる9時
単館上映から始まった自主制作映画が口コミで広がり全国各地で上映されるヒット作に✨
日本アカデミー賞 最優秀作品賞受賞の超話題作🏆#侍タイ pic.twitter.com/WZber4xD0d
幕末の侍が現代の京都で目覚め、電車やコンビニ、撮影所などに遭遇する。
これだけでコメディとして成立しますが、彼の精神性や葛藤が深掘りされることで、ドラマとしても極めて重厚な展開に。
これはまさに「時代設定」という舞台装置がもたらした恩恵です。
ギャップから生まれる笑いと、そこから見えてくる人間性。
その両方が巧みに描かれています。
観客視点と主人公視点が重なる構造
観客と主人公、両方が“現代”に驚いているという構図も特徴的です。
観客は、幕末侍がガラケーに驚く様子や、現代人の価値観に戸惑う姿を見て笑いながら、同時に「私たちはこの時代をどう生きているのか?」という問いを自分にも投げかけられていることに気づきます。
時代劇という文化遺産へのメッセージ
#侍タイムスリッパー
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) July 15, 2025
金曜よる9時✨地上波初
監督・脚本・撮影・照明・編集 他:#安田淳一
殺陣:#清家一斗
床山:#川田政史
時代劇衣装:#古賀博隆 #片山郁江
照明:#土居欣也 #はのひろし
出演:#山口馬木也 #冨家ノリマサ #沙倉ゆうの #峰蘭太郎 #紅萬子 #福田善晴 #井上肇 #田村ツトム #安藤彰則… pic.twitter.com/ZQxyyKsSPq
『侍タイムスリッパー』は、単なる娯楽映画ではありません。
時代劇が衰退していく現代にあって、「本物の侍が現代で再生する」ストーリーは、時代劇文化そのものへのエール。
映画を通じて、“時代劇は終わったコンテンツではない”“新しい形で蘇ることができる”という強いメッセージが込められているのです。
Q&Aで時代設定の疑問を一挙解決!
📺旋風ここに来たれり!☄️
— 小田原シネマ館 | ODAWARA CINEMA | 公式✨ (@odawara_cinema) November 14, 2024
『侍タイムスリッパ―』
小田原シネマ館にて
12/13(金)~公開
たった一館での封切から爆発的大ヒットに!ある会津藩士が落雷によって現代の時代劇撮影所にタイムスリップし、「斬られ役」として生きていくことに!?老若男女問わずその侍魂に胸打たれること間違い無し。 pic.twitter.com/fT1hKG6JRe
Q1. 本作は時代劇?現代劇?
どちらも含んだ“現代時代劇”と言えます。幕末の侍という時代劇的要素を持ちながら、舞台は現代社会。
従来のジャンルに収まらない新しい枠組みです。
Q2. なぜ2007年なのか?なぜ2024年ではない?
- ガラケーやVHSなどアナログ文化がまだ残っていた
- 撮影所や時代劇が身近にあった最後の時代
- 現代すぎると、デジタル描写が強くなりすぎて侍とのギャップがリアルさを失う
これらの要素が組み合わさり、2007年は“ちょうどよい現代”だったのです。
Q3. 他のタイムスリップ作品との違いは?
- 主人公が「侍としてのアイデンティティ」を失わない
- 時代劇文化と真っ向から向き合うテーマ性
- コメディ要素と人間ドラマが高次元で融合
この点で、『信長協奏曲』や『仁』など他のタイムスリップ系作品と一線を画しています。
\『侍タイムスリッパー』関連記事/
まとめ|なぜ『侍タイムスリッパー』の時代設定は現代なのか?
クライマックスの息詰まる長丁場の途中でCMを入れてしまうかどうかで、評価が天と地ほどに分かれそうな気がする。たぶん大丈夫だと思うが。
— 白蔵 盈太/Nirone @「みぎての左甚五郎」文芸社文庫で発売中 (@Via_Nirone7) June 27, 2025
時代劇の片隅で活動している人間として皆様に激推ししますが、「侍タイムスリッパ―」ぜひ見て!全編に時代劇への愛があふれている!私はその熱い愛に泣いた! https://t.co/yU9tcziiSG
『侍タイムスリッパー』は、幕末の侍が現代(2007年)の京都にタイムスリップし、時代劇撮影所で“斬られ役”として新たな人生を歩む物語です。
その舞台設定には次のような意味があります:
- 時代劇の衰退と再生というテーマを描くための装置
- 観客が感情移入しやすい現代を舞台に選びつつ、歴史の重みを持ち込む構造
- ノスタルジーとリアリティを両立できる2007年という時代設定の妙
つまりこの物語は、「時代劇というジャンルが、令和の今こそ再評価されるべき価値を持っている」というメッセージを、現代人に突きつけてくるのです。
歴史の中の人物が、現代で戸惑いながらも懸命に生きる姿。
それは、私たち自身が“今という時代”とどう向き合うかのヒントをくれるように感じられます。
ぜひ、『侍タイムスリッパー』を観て、時代を越えた心の旅に出てみてください!