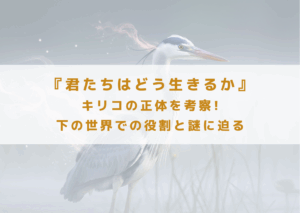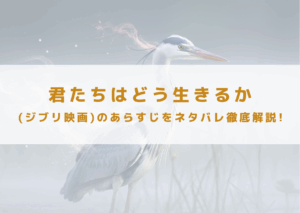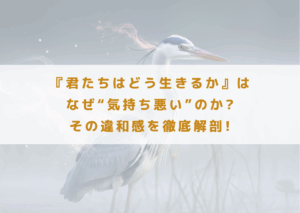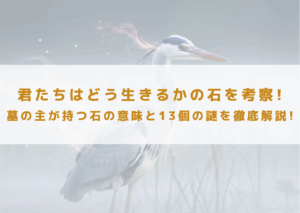宮﨑駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』は、美しくも不可解なビジュアルと、多層的なテーマで観客を魅了しました。
なかでも、
眞人が“触ってはいけない”と言われた人形に手を伸ばすシーンは、見る者の心に静かな違和感と余韻を残します。
「なぜ触ったのか?」「なぜ何も起きなかったのか?」「そもそも人形とは何なのか?」——
本記事では、そんな素朴ながら深い疑問に向き合いながら、眞人の行動と人形の象徴性について徹底的に考察していきます。
ジブリの映画『君たちはどう生きるか』を観ると、元ネタの『君たちはどう生きるか』も気になってきますね!内容はかなり違いますが、映画がインスピレーションを受けたのは間違いないようです!

漫画版が読みやすいのでお勧めです!
本で所有しているとちょっと重いし場所も取りますが、電子書籍なら気軽にサクサク読めちゃいます♪
\ 新規登録で70%オフクーポンもらえる! /

映画鑑賞は年間100本以上・映画ブログ運営4年
中学生の頃に『スターウォーズ』に感動して以降、
映画の沼にハマり続けて20年。
結婚・出産後も年間100本は必ず鑑賞中。
Filmarksアカウントにも鑑賞レビューを掲載中。
【考察】なぜ眞人は「触ってはいけない」と言われた人形に触ったのか?
『君たちはどう生きるか』
— 🐦なげき🐦 (@nagekinoumi) August 18, 2023
このばあちゃんたち好きだったなぁ。
"ばあやが7人いる"っていうインパクトでグッと引き込まれた。 pic.twitter.com/WVZOHqCVwh
異世界に迷い込んだ眞人は、枕元に並べられた“ばあや”に似た人形たちと対面します。
そこで若いキリコから「触ってはいけない」と警告されるものの、眞人はそれを無視して手を伸ばします。
この一連の流れは、ただの子どもらしい行動では済まされない、物語上の深い象徴性を含んでいます。
理由①思春期の好奇心と反抗心
眞人は、父の再婚や新たな環境への順応に苦しむ思春期の少年です。そんな彼にとって、「触ってはいけない」と言われることは逆に興味をかき立てられる対象となりやすい。
多くの観客も、彼が“禁じられたもの”に触れる姿に自身の若き日の感情を重ねたのではないでしょうか。
この行動は、彼の内に芽生える反抗心や、外からのルールに従わない自立心の表出
とも読み取れます。
誰かに言われたから、というよりも、自分の意志で世界を確かめたいという強い欲求。それは彼の成長過程における必然とも言えるのです。
理由②成長物語における“タブー破り”の意味
『君たちはどう生きるか』
— Octopus3 (@amrita_biblion) March 15, 2024
オデュッセウスの旅や古代の神話など、鑑賞者の持つ興味の背景により千通りの顔を見せる物語なのかも。キャンベルの「神話における英雄の行動原理」の全てを通過儀礼のごとく駆け抜ける。記憶の中で何度でも生死を繰り返し永遠に成長を続ける、そんな予感を孕んだ映画でした pic.twitter.com/2OBzK4fq5t
宮﨑駿作品ではしばしば、“してはいけないこと”を主人公が破る場面が描かれます。これは、
物語における通過儀礼であり、成長のきっかけ
でもあります。
眞人が人形に触れるという行為も、このルールに則った行動と捉えられます。
つまりこの「触る」という行動は、彼が新しい世界に踏み込み、その中で自分の足で歩んでいこうとする意志の表れ。
理由③禁忌の相対性と日本文化におけるタブー
宮﨑駿監督『君たちはどう生きるか』を民俗学から読む。鳥と異界、「産屋」のタブー、ワラワラについて | CINRA https://t.co/tYZK1jBo4k
— 畑中章宏@『新・大阪学』 (@akirevolution) March 11, 2024
一方で、「触ってはいけない」とされるものが、必ずしも厳格なタブーとは限らないのもポイントです。
日本文化には、形式的な禁忌が多く存在します。
たとえば箸渡しや畳の縁を踏むこと、神棚を無遠慮に見ることなど、禁忌とされながらも破ったことで必ずしも災厄が訪れるわけではありません。
眞人が触れた人形も、こうした「形式上の禁忌」であった可能性があります。
そのため、触っても“何も起きなかった”という結果が、むしろリアルな心理描写と一致しているのです。
タブーだと言われていても、別に特に何も起きないよね~というのが、逆にリアル、という…。多感な少年はやってはいけないと言われたことを、あえてやってみて、別に何も起きないじゃん!って言われる、あれですね。
【考察】人形に触っても何も起きなかった理由
今日発売の君たちはどう生きるかのグッズが魅力的すぎる🥺
— あやか( ¨̮ ) (@yatomusume) December 9, 2023
この指人形なんて最高すぎる🥹
キリコさんポッケに忍ばせたい😫
ワラワラの人形も欲しぃぃぃぃ😫🫶🏻#どんぐり共和国 pic.twitter.com/p38js6AHI5
タブー破りとか、思春期の反抗心だとか、人形に触ったこと自体には後で意味づけはできるものですが、見ている最中は、「何か恐ろしいことが起きるのでは?」という期待や不安を抱えながら見てましたよね。
しかし、実際には何も起きなかった。これは“肩透かし”に見えるかもしれませんが、実は非常に意味深い演出です。
理由①異世界の“物語的効力”が及ばない存在としての眞人
『君たちはどう生きるか』テレビ初放送が決定!金曜ロードショーにて、5月2日にノーカットで放送予定https://t.co/UO18aMOBWB
— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) April 10, 2025
吉野源三郎氏の描く小説をもとに、ジブリの宮崎駿監督が手がける映画。母を亡くした少年が、謎の「アオサギ」に導かれ異世界を冒険する。翌週には『紅の豚』も放送 pic.twitter.com/L0Auv6Jjyy
この異世界では、特定のルールが作用する“物語的空間”が展開されています。眞人はまだこの異世界に来たばかりですから、
眞人はそのルールから外れた存在、もしくはまだ“その物語に染まっていない存在”
と捉えられます。
だからこそ、禁忌を破っても何の影響も受けない、というわけです。
これは、「ルールに縛られない者が変化を起こす」という宮﨑駿監督の思想とも重なります。
つまり、眞人は“物語を変えていく者”であるがゆえに、旧来のルールには従わない。触れても何も起きないのは、彼がその外側にいることの証明なのです。ちょっと小難しい話ですが、要は眞人は、異世界での物語のルールを変えていく物語の外側の人間だから、物語のルールが通じない人、ということですね。
理由②人形の本質=“守り”であるという象徴性
キリコが語るように、人形はばあやたちが眞人を“見守る”存在です。日本の伝統的な人形信仰でも、人形は単なる装飾ではなく、厄除けや守り神の意味合いを持っています。
眞人が触れても人形が壊れないのは、それが彼に災いをもたらすものではなく、むしろ彼を守る象徴だからです。
人形は不気味さを孕みながらも、静かにその存在感で安心感を与える──そんな“静的な守護”の存在
なのです。
理由③宮﨑駿監督による“肩透かし”の演出手法
◎本日、6月18日は「#おにぎりの日」です。
— ジブリのせかい【非公式ファンサイト】 (@ghibli_world) June 17, 2024
日本最古の「おにぎりの化石」が発見された石川県鹿西町(ろくせいまち)の「ろく(6)」と、毎月18日が「米食の日」であることにちなんで制定されたそうです。
おにぎりと言ったら『千と千尋の神隠し』ですね🍙 pic.twitter.com/NRk8syPNSf
次に考えられるのは演出としての考察ですが、宮﨑作品の多くでは、観客の期待を裏切る“演出の反転”が巧みに仕掛けられます。
「何かが起きそうな場面で、何も起きない」という演出は、現実世界の不確実性や曖昧さ、生きることの予測不能性を映し出すもの
でもあります。
たとえば『千と千尋の神隠し』では、千尋の両親が異世界の食べ物を食べたことで豚に変わってしまい、その瞬間から千尋自身も異界のルールに従わざるを得ない立場に置かれます。しかし同じ異世界でも、リンがくれたおにぎりを食べた千尋には何の変化も起きず、むしろ力を取り戻す重要なきっかけとなります。
このように“何をしても何かが起きる”わけではない、という揺らぎの中で、宮﨑監督は「生きることの理不尽さ」や「物語の外側にある選択の自由」を表現しているのです。
理由④「同一人物は時空を超えて存在できない」説の可能性
暑すぎて…映画館へ。🥵
— すみっこ (@Sumikkoazisai) July 17, 2023
宮崎駿のジブリ
「君たちはどう生きるか」
暑さを感じず快適に映画鑑賞。
満席。
時空を超えたストーリーで、けっこう難しかった。
終わってから、昼食。💞
明日は、さらに暑くなる〜
もう、逃げられない〜。#イマソラ #積雲#君たちはどう生きるか#クリームカレーうどん pic.twitter.com/YW01uXfjsh
一部のファンの間では、「異世界では同一人物が複数存在できず、時を超えて来た場合、片方は人形になる」という仮説がささやかれています。
これは、時間や次元を越えて同じ魂が二重に存在することを禁じる“物語的ルール”の一種と考えられます。
たとえば、現実世界にいるばあやが異世界にも現れてしまったとすれば、同一存在が二重に干渉することになります。
これは世界の秩序や時間の因果律を崩す“物語的パラドックス”を引き起こす可能性があります。
そこで、
この世界では矛盾を回避する手段として「どちらかが人形の姿になる」という変換が行われているのではないか、という考察です。
特に、人形たちは“静止している”のにどこか“生気のようなもの”を感じさせる存在として描かれており、完全な無機物とは思えない演出がなされています。
これは、何らかの記憶や魂の断片が宿っている可能性を示唆していると捉えることもできるでしょう。
ただし、
この説はあくまで補助的な解釈にとどまります。なぜばあやの姿だけが人形化されたのか、眞人が触れても何の影響も受けなかったのか、といった点までは完全には説明できません。
やはり本作全体のテーマから見れば、「守護」「記憶」「心のつながり」といった要素を表す象徴として人形を捉える方が、より自然で深みのある解釈になるのではないでしょうか。
理由⑤『くるみ割り人形』との共通モチーフと影響
今日の夜はこちら。
— あずみずむ (@AsMIsM75) December 9, 2023
12月と言えばくるみ割り人形。
夢のあるストーリーも好きだし、音楽も素晴らしい。
とても楽しみです。#バレエ#くるみ割り人形 pic.twitter.com/IcC57PXtpR
また、『くるみ割り人形』に見られるように、人形は夢と現実をつなぐ橋渡し役としての意味も強く持ちます。
『くるみ割り人形』は、少女クララがくるみ割り人形とともに夢の世界を冒険する物語で、クリスマスに贈られた人形が彼女を異世界へ導く存在になります。
この作品における人形は、単なる玩具ではなく、クララの心の成長や現実との向き合い方を象徴する存在でもあるのです。
眞人の旅もまた、夢のような異世界と現実世界を行き来するプロセスです。
くるみ割り人形のように、“触れること”を通じて魔法が始まり、“見守る存在”が彼を導く。こうした構造的な共通点が、宮﨑監督の演出意図に通じるものとして見ることができるのです。
ジブリの映画『君たちはどう生きるか』を観ると、元ネタの『君たちはどう生きるか』も気になってきますね!内容はかなり違いますが、映画がインスピレーションを受けたのは間違いないようです!

漫画版が読みやすいのでお勧めです!
本で所有しているとちょっと重いし場所も取りますが、電子書籍なら気軽にサクサク読めちゃいます♪
\ 新規登録で70%オフクーポンもらえる! /
\『君たちはどう生きるか』/
\関連記事/
まとめ|人形に触れた眞人の行動が語るものとは?
【6/29(土)~7/5(金)上映作品】
— 早稲田松竹 (@wasedashochiku) June 23, 2024
映画『君たちはどう生きるか』
監督:宮﨑駿
第二次大戦末期。母を火事で失った少年・眞人は、疎開先のお屋敷で生と死が渾然一体となった不思議な世界に分け入っていく――。宮﨑駿が自身の少年時代を重ねて描いた10年ぶりの長編作品。 pic.twitter.com/7x834Ar1Hh
眞人が「触ってはいけない」と言われた人形に触れた行動は、彼の成長、好奇心、そして自己確認の始まりでした。
触っても何も起きなかったのは、彼がその世界のルールに縛られない存在であり、人形自体が“守り”の象徴であったからです。
そして人形は、ばあやの見守り、記憶との結びつき、そして未来への道しるべとして、彼の人生の節目にそっと寄り添います。
このシーンは、単なる演出以上に、「人は誰かに守られている」「モノと心はつながっている」という普遍的なメッセージを秘めているのです。
眞人が手を伸ばしたその瞬間に、観客もまた、自分自身の“触れてはいけないもの”と向き合うような気持ちになる──それこそが、この映画が放つ静かな魔法なのかもしれません。